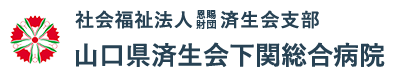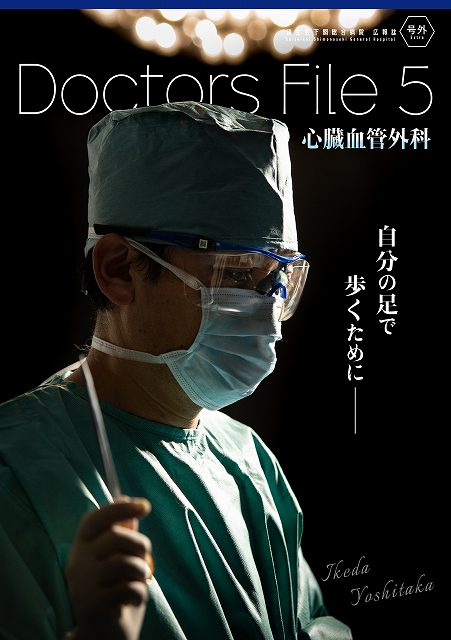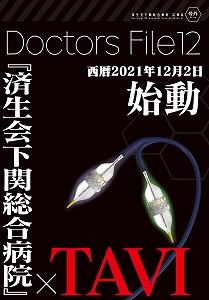心臓血管外科・ウルフーオオツカ低侵襲心房細動手術センターin山口・九州
- 1階
- フロアマップ
- 概要・特色
- スタッフ紹介
- 外来担当医表
- 診療実績
- MICS手術と不整脈治療
- ウルフーオオツカ低侵襲心房細動手術センターin山口・九州
- 下肢静脈瘤について
- TAVI(経カテーテル的大動脈弁置換術)について
概要・特色
山口県西部の心臓血管外科領域の核として、年間約170-180例の心臓大血管の手術と、約100例の末梢血管の手術を施行しております。
<開心術>
単独冠動脈バイパス術は低侵襲で人工心肺を用いないOff Pump CABGをほぼ全例に施行しております。また、バイパスに用いるグラフトは、ほぼ全例に長期開存率の優れている内胸動脈グラフトを用いております。
近年高齢化に伴い、80歳以上の大動脈弁狭窄症の患者さんが増えております。このような高齢の患者さんにも、安全に大動脈弁置換術を受けていただいております。最近では92歳の患者さんに大動脈弁置換術を行い、お元気で退院していただいております。
僧帽弁閉鎖不全症に対しては、高齢の患者さんでも弁形成術を第一選択として実施しております。
また、単独僧帽弁形成術は原則として皮膚切開の小さい(7-10cm)低侵襲のMICS(Minimally invasive cardiac surgery)を行っております。この手術ですと傷が小さく、術後の疼痛も軽いです。
弓部大動脈瘤、大動脈解離の患者さんに対しては、ご高齢(最高89歳)の患者さんに対しても手術を行い、元気に退院していただいております。
<ステントグラフト内挿術>
胸部大動脈瘤、腹部大動脈瘤に対しては、低侵襲なステントグラフト治療を実施しています。ステントグラフトはこれまで手術不能と言われきた高齢の患者さんや手術既往のある患者さんに対しても実施可能なことが多く、入院期間も1週間以内と短いことが特徴です。
なお、急性大動脈解離など緊急手術には随時対応しております。いつでもご連絡下さい。
当施設は以下の施設基準を満たしています。
心臓血管外科専門医認定機構の基幹施設
胸部大動脈瘤ステントグラフト実施施設
腹部大動脈瘤ステントグラフト実施施設
当院は日本成人心臓血管外科手術データベースならびに日本先天性心臓血管外科手術データベース参加施設です。患者さんのデータは匿名で上記データベースに登録させていただくことが義務付けられております。個人が特定されることはありませんが、データ登録を望まれない方はお申し出ください。詳しくはホームページをご参照ください。
http://www.jacvsd.umin.jp/about.html
http://jccvsd.umin.jp/
スタッフ紹介

伊東 博史 副院長 兼 心臓血管外科科長
山口大学 臨床准教授
心臓血管外科専門医認定機構 基幹施設修練責任者
日本心臓血管外科学会 評議員
日本心臓血管外科学会 専門医
日本外科学会:指導医・専門医
日本胸部外科学会:認定医・正会員
関西胸部外科学会 評議員
経カテーテル的大動脈弁置換術指導医
低侵襲心臓手術認定医

髙橋 雅弥
日本外科学会 専門医
日本心臓血管外科 専門医

山下 修
日本外科学会 専門医
日本心臓血管外科学会 専門医
日本脈管学会 脈管専門医・指導医
日本血管外科学会 血管内治療認定医

池 創一
日本外科学会 専門医
日本脈管学会 専門医
日本再生医療学会 認定医
外来担当医表
外来窓口:[1階]12番 心臓血管外科
令和7年4月1日より
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 心臓大血管 | 午前 |
担当医
|
- |
髙橋雅弥
|
- |
伊東博史
|
| 末梢血管・静脈瘤 | 午前 | 山下 修 | - | - | - | 池 創一 |
| ウルフオオツカ外来 | 午前 | - | - | 伊東博史 | - | - |
- ※外来担当表は、予告なく変更される場合がございます。来院前に必ずお電話でご確認ください。
- ※休診予定については、お電話にてご確認ください。連絡先:083-262-2300(代表)
診療実績
MICS手術と不整脈治療
※MICS Minimally Invasive Cardiac Surgery 低侵襲心臓手術についてはこちら
ウルフーオオツカ低侵襲心房細動手術センターin山口・九州
現在(2024年8月時点)までに当院の伊東医師は他院での指導を含めて200例以上施行し、この手技開発者である大塚先生(ニューハートワタナベ国際病院所属)に次いで2番目の症例数となりました。
これまでの成果を2023年5月31日(水)~6月3日(土)に開催された国際低侵襲心臓血管外科学会(ISMICS)in Bostonで発表しました。
(国際低侵襲心臓血管外科学会 大会プログラム https://meetings.ismics.org/program/2023/PC11.cgi )
ご相談は下記のメール
h-ito@simo.saiseikai.or.jp
※Wolf-Ohtsuka法(WO手術 ウルフ・オオツカ法)についてはこちら