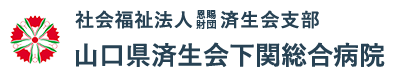患者の意思決定支援委員会
患者の意思決定支援委員会について
この委員会は、当院が患者さんの気持ちや考えに寄り添う医療をするためにつくられました。
そのためには私たち医療従事者が、患者さんの気持ちや考えをよく知ることが必要です。 しかし、現実はどうでしょう?
病院のなかで患者さんの気持ちや考えを聴く時間はそう多くはありません。 そこで患者さんに記入していただく、「私の大切にしたいこと」と「私の医療に対する希望」 という名の2つの文書を準備 しました。いずれもチェック形式で簡便に記入でき、しかも詳しく書きたいことは自由に記載もできます。
「私の大切にしたいこと」は患者さんの価値観 や人生観を知る一助となり、「私の医療に対する希望」は人生の最終段階にさしかかった時の医療に対する具体的な希望を知ることができます。
これらを活用しながら、患者さんとよく話し合って、気持ちや考えに寄り添う医療の実現に努めていこうと思います。
そのためには私たち医療従事者が、患者さんの気持ちや考えをよく知ることが必要です。 しかし、現実はどうでしょう?
病院のなかで患者さんの気持ちや考えを聴く時間はそう多くはありません。 そこで患者さんに記入していただく、「私の大切にしたいこと」と「私の医療に対する希望」 という名の2つの文書を準備 しました。いずれもチェック形式で簡便に記入でき、しかも詳しく書きたいことは自由に記載もできます。
「私の大切にしたいこと」は患者さんの価値観 や人生観を知る一助となり、「私の医療に対する希望」は人生の最終段階にさしかかった時の医療に対する具体的な希望を知ることができます。
これらを活用しながら、患者さんとよく話し合って、気持ちや考えに寄り添う医療の実現に努めていこうと思います。
「私の大切にしたいこと」
「私の医療に対する希望」
患者さん・ご家族へのお願い
私たちは誰もが永遠の命はないとわかっています。そして、誰もが自分の命を最期まで自分らしく生きたいと考えています。 でも、いつかはやってくる自分の人生の最期について考えている人はどのくらいいるでしょうか。 最期まで自分らしく過ごすには、元気なうちに準備が必要です。
そこで、人生の終末期に自分が受ける医療やケアについて考えてみましょう。そして自分の考えを周りの人に知ってもらうことが重要です。それには話し合うことが必要です。
私たちは、みなさんの医療に対する希望に寄り添います。
そこで、人生の終末期に自分が受ける医療やケアについて考えてみましょう。そして自分の考えを周りの人に知ってもらうことが重要です。それには話し合うことが必要です。
私たちは、みなさんの医療に対する希望に寄り添います。
当院における人生の最終段階における適切な意思決定支援に関する指針
1. 当院における人生の最終段階における適切な意思決定支援に関する指針
本指針は、厚生労働省の「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」を規範とし策定する。
「私の大切にしたいこと」や、患者・家族との関わりの中で、患者の人生観や価値観等をできるだけ把握するように努める。
(1) 私たちは、患者さんの意思を尊重した医療を行います。
入院時に「私の大切にしたいこと」を記入してもらい、患者の人生観や価値観をできる限り把握する。
(2) 意思決定に必要な病状を患者さんに丁寧に説明します。
患者本人・家族に、病状・入院の目的などの説明を適切に行なう。
(3) 医療チームとして、患者さんの意思決定を支援します。
医師、看護師、その他多職種で、その時点での患者の意思・希望などを話し合い、必要に応じて適宜介入する。
(4) 繰り返し話し合いをします。
病状が変化したとき、患者の意思が変わったときには何度でも話し合う。
(5) 患者さん・家族の気持ちに配慮しながら「もしも・・・」に備えた話し合いもします。
意思決定代理人を決め、「私の医療に対する希望」に沿い、延命処置についても話し合う。
(6) 話し合った内容をその都度カルテに記録し共有できるようにします。
患者の医療・ケアに対する意思決定の内容や意思決定代理人を、分かりやすく電子カルテに記録する。
(7) <患者の意思決定支援委員会>が検討し助言します。
医療・ケア内容の決定が困難な場合は、主治医の希望により、多職種で編成されている<患者の意思決定支援委員会>で慎重に話し合う。
2. 用語の説明
(1) 人生の最終段階の定義
1) 患者が適切な治療を受けても回復の見込みがなく、かつ、死期が間近と判定された状態(老衰を含め、回復が期待されないと予測する生存期間)。
(2) 当院オリジナルの関連書類
人生の最終段階にこそ最も人としての尊厳を守る為に、患者の意思を引き出す仕組みとして下記2種類の書類を準備。
1) 「私の大切にしたいこと」
人生観・価値観・受けたい治療やケアを、家族や医療チームと共有する。
2) 「私の医療に対する希望」
迎える場所・蘇生術・痛みの緩和などを意思表示し、家族や医療チームと共有する。
(3) 医療チーム
・医師・看護師・MSW、その他患者の病状に応じて介入が必要な医療者。
本指針は、厚生労働省の「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」を規範とし策定する。
「私の大切にしたいこと」や、患者・家族との関わりの中で、患者の人生観や価値観等をできるだけ把握するように努める。
(1) 私たちは、患者さんの意思を尊重した医療を行います。
入院時に「私の大切にしたいこと」を記入してもらい、患者の人生観や価値観をできる限り把握する。
(2) 意思決定に必要な病状を患者さんに丁寧に説明します。
患者本人・家族に、病状・入院の目的などの説明を適切に行なう。
(3) 医療チームとして、患者さんの意思決定を支援します。
医師、看護師、その他多職種で、その時点での患者の意思・希望などを話し合い、必要に応じて適宜介入する。
(4) 繰り返し話し合いをします。
病状が変化したとき、患者の意思が変わったときには何度でも話し合う。
(5) 患者さん・家族の気持ちに配慮しながら「もしも・・・」に備えた話し合いもします。
意思決定代理人を決め、「私の医療に対する希望」に沿い、延命処置についても話し合う。
(6) 話し合った内容をその都度カルテに記録し共有できるようにします。
患者の医療・ケアに対する意思決定の内容や意思決定代理人を、分かりやすく電子カルテに記録する。
(7) <患者の意思決定支援委員会>が検討し助言します。
医療・ケア内容の決定が困難な場合は、主治医の希望により、多職種で編成されている<患者の意思決定支援委員会>で慎重に話し合う。
2. 用語の説明
(1) 人生の最終段階の定義
1) 患者が適切な治療を受けても回復の見込みがなく、かつ、死期が間近と判定された状態(老衰を含め、回復が期待されないと予測する生存期間)。
(2) 当院オリジナルの関連書類
人生の最終段階にこそ最も人としての尊厳を守る為に、患者の意思を引き出す仕組みとして下記2種類の書類を準備。
1) 「私の大切にしたいこと」
人生観・価値観・受けたい治療やケアを、家族や医療チームと共有する。
2) 「私の医療に対する希望」
迎える場所・蘇生術・痛みの緩和などを意思表示し、家族や医療チームと共有する。
(3) 医療チーム
・医師・看護師・MSW、その他患者の病状に応じて介入が必要な医療者。
令和6年5月1日施行
山口県済生会下関総合病院