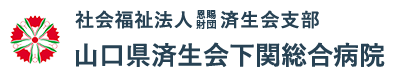子宮体がん
がんの組織型や分化度(悪性度)からみた種類
がんの組織型の違いによって、類内膜腺がん、漿液性腺がん、明細胞腺がん、粘液性腺がんなどに分けられますが、類内膜腺癌が子宮体癌の80%以上を占め、他のがんに比べて予後が比較的良好です。
類内膜腺がんは、がんのタチの悪さから悪性度が低く予後が比較的良好な高分化型(G1:グレード1)、次に中分化型(G2:グレード2)、悪性度が高く増殖・転移が速く予後が悪い低分化型(G3:グレード3)に分けられます。
よって、がんの進行期だけではなく、組織型や分化度によって治療法を決めていきます。
類内膜腺がんは、がんのタチの悪さから悪性度が低く予後が比較的良好な高分化型(G1:グレード1)、次に中分化型(G2:グレード2)、悪性度が高く増殖・転移が速く予後が悪い低分化型(G3:グレード3)に分けられます。
よって、がんの進行期だけではなく、組織型や分化度によって治療法を決めていきます。
原因、疫学
子宮体がんは若年女性に発生することは比較的少なく、閉経期前後の40歳代後半から増加して50~60歳代にピークを迎えます。
未婚、未妊、肥満などの方に子宮体がんが発症しやすいと言われていますが、子宮体がんの多くは女性ホルモンの高エストロゲン状態が大きな影響を与えると考えられています。何らかの原因でエストロゲンが長期的。持続的に過剰に産生されると、子宮内膜が刺激を受け続けて前がん病変としては子宮内膜異型増殖症が発症し、その一部が子宮体がんになると考えられています。
閉経後でもエストロゲンは脂肪細胞でも産生されるため、高脂血症も子宮体がんと関係が深いとされ、食生活の欧米化も子宮体がん増加の要因となっています。欧米化も子宮体がん増加の要因となっています。
未婚、未妊、肥満などの方に子宮体がんが発症しやすいと言われていますが、子宮体がんの多くは女性ホルモンの高エストロゲン状態が大きな影響を与えると考えられています。何らかの原因でエストロゲンが長期的。持続的に過剰に産生されると、子宮内膜が刺激を受け続けて前がん病変としては子宮内膜異型増殖症が発症し、その一部が子宮体がんになると考えられています。
閉経後でもエストロゲンは脂肪細胞でも産生されるため、高脂血症も子宮体がんと関係が深いとされ、食生活の欧米化も子宮体がん増加の要因となっています。欧米化も子宮体がん増加の要因となっています。
症状
子宮体がんも初期では無症状なことが多く、がんの進行と共に不正出血や帯下の増加などの症状があらわれてくることが多いです。特に閉経期以降の出血は注意が必要です。しかし、閉経によって腟粘膜が萎縮することに伴う良性の出血(萎縮性腟炎や老人性腟炎)も多いので、出血があれば悩まずに婦人科を受診することを勧めます。
検査
子宮体がんでも細胞診(子宮内膜をブラシなどで擦って細胞を採取)が大切な検査になります。ドック健診や集団検診での子宮がん検診とは通常子宮頸がん検診のことで子宮体がん健診は含まれていないことが多いので注意して下さい。細胞診での子宮体がんの診断率は約90%とされています。また、子宮体部細胞診で、卵巣がんや卵管がんが見つかることもあります。細胞診で異常が疑われれば、子宮内膜組織生検(簡単な麻酔をして子宮内膜の組織を採取する検査)を行って診断をします。この結果、がんと診断されれば進行状態を調べるために画像診断(MRI検査やCT検査など)を行います。また腫瘍マーカー検査などが追加されます。
治療
子宮体がんでは、組織型、分化度、リンパ節転移の有無、卵巣転移の有無が重要な予後因子となっています。
手術可能な子宮体癌では手術が原則です。
I期(がんが子宮体部にとどまっているもの)の場合、類内膜腺がんでG1,G2かつ筋層浸潤が1/2以下であれば、単純子宮全摘出+両側付属器摘出(両側の卵巣・卵管摘出)が基本となり、その他の場合はリンパ節郭清や大網切除が追加されます。
II期(がんが頸部間質に浸潤するが子宮にとどまっているもの)の場合、準広汎あるいは広汎子宮全摘出+両側付属器摘出+リンパ節郭清+大網切除が基本となります。
しかし、I期、II期であっても高齢者や合併症のため手術が困難な患者さんには放射線治療も考慮されます。
若年の場合で妊娠を強く希望される方には、高分化型の類内膜腺がんで筋層浸潤がない場合にはホルモン療法による子宮温存をおこなうこともあります。この場合は、再発の危険性があるので厳重な定期健診が必要です。
がんが子宮の外に広がっているIII期、IV期の場合でも、手術可能な場合には手術を行いますが、手術不可能な場合には、抗がん剤による化学療法、放射線治療、ホルモン療法などが選択肢となります。治療開始時に広範囲に転移を認める症例では、ネオアジュバント化学療法(抗がん剤投与)を行い、その後手術が可能になる範囲まで腫瘍が縮小した場合に手術を行う場合もあります。前がん病変である子宮内膜異型増殖症は、放置するとがん化しますので、治療の基本は単純子宮全摘出ですが、妊娠を希望する患者さんに対してはホルモン療法による子宮温存を行います。
手術可能な子宮体癌では手術が原則です。
I期(がんが子宮体部にとどまっているもの)の場合、類内膜腺がんでG1,G2かつ筋層浸潤が1/2以下であれば、単純子宮全摘出+両側付属器摘出(両側の卵巣・卵管摘出)が基本となり、その他の場合はリンパ節郭清や大網切除が追加されます。
II期(がんが頸部間質に浸潤するが子宮にとどまっているもの)の場合、準広汎あるいは広汎子宮全摘出+両側付属器摘出+リンパ節郭清+大網切除が基本となります。
しかし、I期、II期であっても高齢者や合併症のため手術が困難な患者さんには放射線治療も考慮されます。
若年の場合で妊娠を強く希望される方には、高分化型の類内膜腺がんで筋層浸潤がない場合にはホルモン療法による子宮温存をおこなうこともあります。この場合は、再発の危険性があるので厳重な定期健診が必要です。
がんが子宮の外に広がっているIII期、IV期の場合でも、手術可能な場合には手術を行いますが、手術不可能な場合には、抗がん剤による化学療法、放射線治療、ホルモン療法などが選択肢となります。治療開始時に広範囲に転移を認める症例では、ネオアジュバント化学療法(抗がん剤投与)を行い、その後手術が可能になる範囲まで腫瘍が縮小した場合に手術を行う場合もあります。前がん病変である子宮内膜異型増殖症は、放置するとがん化しますので、治療の基本は単純子宮全摘出ですが、妊娠を希望する患者さんに対してはホルモン療法による子宮温存を行います。