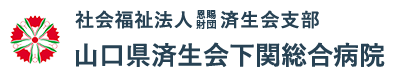身体的拘束等最小化のための指針
1.当院における身体的拘束最小化に関する基本的な考え方
身体的拘束は、身体的・心理的・社会的弊害をもたらすため、身体的拘束をしないためのケアを行い、実施に関しては慎重に判断する必要がある。身体的拘束により、高齢者の身体機能は低下し、寝たきりにつながるおそれがあり、QOLを損なう危険性を有している。
済生会下関総合病院(以下、当院)では、患者のサービスにあたっては、患者の尊厳と主体性を尊重し、身体的拘束を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが拘束による身体的・精神的弊害を理解し、身体的拘束の廃止に向けた意識をもち、緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束をしない診療・看護の提供に努める。上記の「緊急やむを得ない場合」とは、身体的拘束の適応3要件を全て満たす場合をいう。尚、適応3要件が改善した場合は速やかに解除することとする。
2.身体的拘束最小化のための体制
1)身体的拘束最小化チームの設置
(1)身体的拘束最小化チームの構成員
医師(専任)
看護師(専任)(認知症看護認定看護師、認知症ケア委員会委員長、せん妄対策委員、認知症ケア専門士等)
薬剤師(専任)
社会福祉士・精神保健福祉士(専任)
(2)身体的拘束最小化チームの業務
①身体的拘束の実施状況を把握し、管理者を含む職員に定期的に周知・徹底する。
・各病棟看護師は、「認知症患者・身体的拘束患者・離床センサー使用患者一覧表」に、ラウンド対象となる患者
名等を記載する。
・身体的拘束最小化チームは、週1回程度病棟をラウンドし、身体的拘束を実施している患者について、以下のこと
をカンファレンスで検討し、指導・助言を行う。チームラウンドでの検討内容を電子カルテに記載する。
→身体的拘束の必要性の判断(3要件のすべてを満たしているかどうか)
・患者の状態・状況を確認(身体的拘束の内容、目的、理由、実施状況と期間)し、解除に向けたケアの方策の検討
・【適正な薬剤の検討】:必要時に主治医から当院非常勤のリエゾン科医師へ診察を依頼し、連携し、情報共有を行う。
・身体的拘束最小化チームの看護師は、各部署の「認知症患者・身体的拘束患者・離床センサー使用患者一覧表」
より、身体的拘束を実施している患者の人数、実施方法、実施期間を把握する。また、患者の看護記録から身体
的拘束に関する記録(様態、時間、患者の心身の状況、緊急やむを得ない理由、身体的拘束の解除に向けたカン
ファレンス)を確認する。
・月1回(第2月曜日ラウンド後)、チームメンバーで身体的拘束の推移やケアの方法、適正な薬剤等について会議
を開催する。
・身体拘束の実施状況、拘束率などについて報告書を作成し、管理者ほか職員へ周知を図る。
②本指針の定期的な見直し(年1回程度)
③全職員を対象とした身体的拘束の最小化に関する研修の実施(年1~2回)
・当指針の周知を図るとともに、身体的拘束をしない取り組み事例などを研修を通し、共有し、実践に生かせるよ
うにする。
3.身体的拘束最小化に向けての基本方針
・患者または他の患者等の生命または身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束は行わない。
・身体的拘束を実施するかどうかは、職員個々の判断ではなく、当該患者に関わる医師、看護師等、当該患者に関わ
る複数の職員で検討する。
・やむを得ず身体的拘束を実施する場合であっても、当該患者の生命及び身体の保護に重点を置いた行動の制限であ
り、代替の方法が見出されるまでの間のやむを得ない対応として行われるものであることから、速やかに解除する
よう努める。
・身体的拘束中は二次的な身体障害の予防に努める。
1)身体的拘束に該当する具体的行為
医療サービスの提供にあたって、患者の身体を拘束し、その行動を抑制する行為とする。入院患者の行動を制限す
る具体的行為にあたるものとして、厚生労働省が「身体的拘束ゼロへの手引き」(平成13年3月)の中であげている
行為を下に示す。
② 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
③ 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
④ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。
⑤ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしら ないように、手指の機能を制限するミト
ン型の手袋等をつける。
⑥ 車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける。
⑦ 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する。
⑧ 脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
⑨ 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で
⑩ 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
⑪ 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。
「身体的拘束ゼロへの手引き」平成13年3月:厚生労働省「身体抑制ゼロ作戦推進会議」より
(1)当院での身体的拘束に該当する具体的行為として、
①抑制帯 ②ミトン ③4点柵など他上記にあたる行為が挙げられる。
(2)離床センサーは、患者のそばに付き添い、移動の介助をすることで、患者の転倒予防を目的とする。
【小児について】
「処置時の一時的」「点滴時のシーネ固定」「ミトンを用いた身体的拘束」は行動制限に該当するが、小児科領域診療において日常安全な治療を遂行するために使用されている手技・方法であるため、医師あるいは看護師が保護者に口頭で説明し、同意を得ることとし、文書による説明と同意は不要とする。
2)身体的拘束を実施する場合の実施基準
【身体的拘束の適応3要件】
<緊急やむを得ない場合とは> ※以下の①~③すべてを満たすこと
厚生労働省「身体的拘束等の適正化の推進」より
(1)身体的拘束が緊急やむを得ない場合、看護師は医師へ患者の状況を報告する。
できる限り、医師や他職種と共に患者の状況を確認する。(年齢、身体状況、環境、治療の側面)
3)身体的拘束の実施手順
(1)緊急やむを得ないと判断した場合、別紙「身体的拘束を行う場合の判断・実施フローチャート」を厳守し、医
師へ報告後、医師が身体的拘束を必要であると判断したうえで、医師の指示のもとに行う。医師(医師が不在の
場合は看護師)は患者や家族に対し、身体的拘束の必要性(目的、理由、拘束の期間等)を説明し、開始の同意
を得る。同意書を用いて説明し、サインをもらう。同意書の実施期間は、最長2週間とする。期間の延長が必要な
場合、再度患者または家族に説明し、同意書にサインをもらう。
(2)医師が身体的拘束の開始の指示を出す。看護師は指示を確認する。
(3)身体的拘束を開始する際は、①様態(状態)、②開始時間、③患者の心身の状況、④緊急やむを得ない理由、⑤
具体的内容を経過記録に記録する。
(4)看護師は、抑制具による身体の状況(身体的弊害がないか)など、身体的拘束が安全に行われているのかを随時
観察し、その旨を2時間毎、看護記録に記録する。異変が認められた場合、速やかに医師に報告し、指示を仰ぐ。
(5)身体的拘束中は、1日に1回以上、身体的拘束の解除に向けたカンファレンスを実施し、その内容を経過記録に
記録する。
<カンファレンスのポイント>
・現在の治療の状況、医師の指示の安静度はどうか
・現在の患者の心身の様子はどうか
・緊急やむを得ない3要件すべてに当てはまっている状況か
・現在行っているケア・対応はどのようなものか
・回避・軽減(代替)方法はないか(例:点滴は必要か、注射は内服に変更できないか、胃管・尿道カテーテ
ル留置の必要性はどうか、安静度は拡大できないのか、病室の移動はできないのか、生活リズム確立のため
どんなケアができるのか)
・今後どのようにして身体的拘束を解除していくか
(6)医師は、身体的拘束の適応3要件が改善した場合、または身体的拘束が不要と判断した場合、医師は身体的拘束
の終了(解除)の指示を出す。看護師は指示を確認し、速やかに解除する。看護師判断で解除した場合は、事後
に医師へ報告し、指示を受けることとする。
→解除基準:身体的拘束の適応3要件が改善し、診療上の安全確保のための身体的拘束が解決できたとき、医師の指
示のもとに解除する。
①治療・処置が終了、または方法を検討して危機が回避されたとき
②患者が治療を理解し、協力が得られるようになったとき
③家族などの協力が得られるようになったとき
④回避・軽減(代替)方法が実施されたとき
4)身体的拘束を最小化するための日常ケアにおける基本方針
・身体的拘束を行う必要性を生じさせないために日常的に以下のことに取り組む。
(1)患者主体の行動や尊厳を尊重する。
(2)言葉や応対などで、患者の精神的な自由を妨げないよう努める。
(3)患者の思いをくみとり、患者の意向に沿ったサービスを提供し、多職種協働で丁寧な対応に努める。
(4)身体的拘束を誘発する原因の特定と除去に努める。
(5)基本的なケアを行い、生活リズムを整える。①起きる、②食べる、③排泄する、④清潔にする、⑤活動する、
という5つの事項について、患者個々に合った十分なケアを提供する。
5)身体的拘束以外の患者の行動を制限する行為の最小化について
・行動を制限する目的での薬剤の使用は、治療・療養上必要な場合を除き行わない。
・患者に対し、行動を制限するような言動(発言や制止など)がないよう常に意識しながら対応する。
6)鎮静を目的とした薬物の適正使用について
・当院のデルタプログラムに沿った薬剤を検討する。
・認知症患者の暴力や不穏に対する薬物療法ではリスペリドンが推奨されている。
・認知症患者の性的脱抑制、不適切な性的行動に対する薬物療法では、SSRI、非定型抗精神病薬、トラゾドンが推奨
される。
・薬物を使用した場合、その効果と副作用の評価を行い、薬物の種類、投与量、投与時間、投与方法などを調整する。
4.身体的拘束最小化、低減のための職員教育
1)全職員に、当指針を周知する。
2)定期的に、身体的拘束最小化に関する研修会を年1~2回開催する。全職員を対象とし年1回は受講できるようe-ラ
ーニング等も活用する。
3)研修の実施にあたっては、研修主催者が実施日・実施場所・参加人数・研修名・内容(研修概要)及び研修後アン
ケートを記載した記録を作成する。
5.患者・家族への不安の軽減への配慮
説明者は、身体的拘束・行動制限が人間の尊厳に関わる重大な問題であることを認識しているべきで、このことが患
者・家族に伝わることが必要である。そのためには、患者の状況について的確に説明することにより、安全確保のた
めに、やむを得ず実施することに納得が得られる必要がある。特に、看護師には、実施中の患者・家族の思いを受け
止めるような態度や言動が求められる。
解除に向けた検討の場やカンファレンスで、観察項目の確認だけでなく、患者・家族の不安を受け止めた内容の検討
が必要である。
(附 則)
この指針は、令和6年5月28日から施行する。
身体的拘束は、身体的・心理的・社会的弊害をもたらすため、身体的拘束をしないためのケアを行い、実施に関しては慎重に判断する必要がある。身体的拘束により、高齢者の身体機能は低下し、寝たきりにつながるおそれがあり、QOLを損なう危険性を有している。
済生会下関総合病院(以下、当院)では、患者のサービスにあたっては、患者の尊厳と主体性を尊重し、身体的拘束を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが拘束による身体的・精神的弊害を理解し、身体的拘束の廃止に向けた意識をもち、緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束をしない診療・看護の提供に努める。上記の「緊急やむを得ない場合」とは、身体的拘束の適応3要件を全て満たす場合をいう。尚、適応3要件が改善した場合は速やかに解除することとする。
2.身体的拘束最小化のための体制
1)身体的拘束最小化チームの設置
(1)身体的拘束最小化チームの構成員
医師(専任)
看護師(専任)(認知症看護認定看護師、認知症ケア委員会委員長、せん妄対策委員、認知症ケア専門士等)
薬剤師(専任)
社会福祉士・精神保健福祉士(専任)
(2)身体的拘束最小化チームの業務
①身体的拘束の実施状況を把握し、管理者を含む職員に定期的に周知・徹底する。
・各病棟看護師は、「認知症患者・身体的拘束患者・離床センサー使用患者一覧表」に、ラウンド対象となる患者
名等を記載する。
・身体的拘束最小化チームは、週1回程度病棟をラウンドし、身体的拘束を実施している患者について、以下のこと
をカンファレンスで検討し、指導・助言を行う。チームラウンドでの検討内容を電子カルテに記載する。
→身体的拘束の必要性の判断(3要件のすべてを満たしているかどうか)
・患者の状態・状況を確認(身体的拘束の内容、目的、理由、実施状況と期間)し、解除に向けたケアの方策の検討
・【適正な薬剤の検討】:必要時に主治医から当院非常勤のリエゾン科医師へ診察を依頼し、連携し、情報共有を行う。
・身体的拘束最小化チームの看護師は、各部署の「認知症患者・身体的拘束患者・離床センサー使用患者一覧表」
より、身体的拘束を実施している患者の人数、実施方法、実施期間を把握する。また、患者の看護記録から身体
的拘束に関する記録(様態、時間、患者の心身の状況、緊急やむを得ない理由、身体的拘束の解除に向けたカン
ファレンス)を確認する。
・月1回(第2月曜日ラウンド後)、チームメンバーで身体的拘束の推移やケアの方法、適正な薬剤等について会議
を開催する。
・身体拘束の実施状況、拘束率などについて報告書を作成し、管理者ほか職員へ周知を図る。
②本指針の定期的な見直し(年1回程度)
③全職員を対象とした身体的拘束の最小化に関する研修の実施(年1~2回)
・当指針の周知を図るとともに、身体的拘束をしない取り組み事例などを研修を通し、共有し、実践に生かせるよ
うにする。
3.身体的拘束最小化に向けての基本方針
・患者または他の患者等の生命または身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束は行わない。
・身体的拘束を実施するかどうかは、職員個々の判断ではなく、当該患者に関わる医師、看護師等、当該患者に関わ
る複数の職員で検討する。
・やむを得ず身体的拘束を実施する場合であっても、当該患者の生命及び身体の保護に重点を置いた行動の制限であ
り、代替の方法が見出されるまでの間のやむを得ない対応として行われるものであることから、速やかに解除する
よう努める。
・身体的拘束中は二次的な身体障害の予防に努める。
1)身体的拘束に該当する具体的行為
医療サービスの提供にあたって、患者の身体を拘束し、その行動を抑制する行為とする。入院患者の行動を制限す
る具体的行為にあたるものとして、厚生労働省が「身体的拘束ゼロへの手引き」(平成13年3月)の中であげている
行為を下に示す。
【身体的拘束禁止の対象となる具体的な行為】
① 徘徊しないように、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。② 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
③ 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
④ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。
⑤ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしら ないように、手指の機能を制限するミト
ン型の手袋等をつける。
⑥ 車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける。
⑦ 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する。
⑧ 脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
⑨ 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で
⑩ 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
⑪ 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。
「身体的拘束ゼロへの手引き」平成13年3月:厚生労働省「身体抑制ゼロ作戦推進会議」より
(1)当院での身体的拘束に該当する具体的行為として、
①抑制帯 ②ミトン ③4点柵など他上記にあたる行為が挙げられる。
(2)離床センサーは、患者のそばに付き添い、移動の介助をすることで、患者の転倒予防を目的とする。
【小児について】
「処置時の一時的」「点滴時のシーネ固定」「ミトンを用いた身体的拘束」は行動制限に該当するが、小児科領域診療において日常安全な治療を遂行するために使用されている手技・方法であるため、医師あるいは看護師が保護者に口頭で説明し、同意を得ることとし、文書による説明と同意は不要とする。
2)身体的拘束を実施する場合の実施基準
【身体的拘束の適応3要件】
<緊急やむを得ない場合とは> ※以下の①~③すべてを満たすこと
| ① | 切迫性 | 利用者本人又は他の利用者等の生命、身体、権利が危険にさらされる可能性が著しく高い。 |
| ② | 非代替性 | 身体的拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がない。 |
| ③ | 一時性 | 身体的拘束その他の行動制限が一時的である。 |
(1)身体的拘束が緊急やむを得ない場合、看護師は医師へ患者の状況を報告する。
できる限り、医師や他職種と共に患者の状況を確認する。(年齢、身体状況、環境、治療の側面)
3)身体的拘束の実施手順
(1)緊急やむを得ないと判断した場合、別紙「身体的拘束を行う場合の判断・実施フローチャート」を厳守し、医
師へ報告後、医師が身体的拘束を必要であると判断したうえで、医師の指示のもとに行う。医師(医師が不在の
場合は看護師)は患者や家族に対し、身体的拘束の必要性(目的、理由、拘束の期間等)を説明し、開始の同意
を得る。同意書を用いて説明し、サインをもらう。同意書の実施期間は、最長2週間とする。期間の延長が必要な
場合、再度患者または家族に説明し、同意書にサインをもらう。
(2)医師が身体的拘束の開始の指示を出す。看護師は指示を確認する。
(3)身体的拘束を開始する際は、①様態(状態)、②開始時間、③患者の心身の状況、④緊急やむを得ない理由、⑤
具体的内容を経過記録に記録する。
(4)看護師は、抑制具による身体の状況(身体的弊害がないか)など、身体的拘束が安全に行われているのかを随時
観察し、その旨を2時間毎、看護記録に記録する。異変が認められた場合、速やかに医師に報告し、指示を仰ぐ。
(5)身体的拘束中は、1日に1回以上、身体的拘束の解除に向けたカンファレンスを実施し、その内容を経過記録に
記録する。
<カンファレンスのポイント>
・現在の治療の状況、医師の指示の安静度はどうか
・現在の患者の心身の様子はどうか
・緊急やむを得ない3要件すべてに当てはまっている状況か
・現在行っているケア・対応はどのようなものか
・回避・軽減(代替)方法はないか(例:点滴は必要か、注射は内服に変更できないか、胃管・尿道カテーテ
ル留置の必要性はどうか、安静度は拡大できないのか、病室の移動はできないのか、生活リズム確立のため
どんなケアができるのか)
・今後どのようにして身体的拘束を解除していくか
(6)医師は、身体的拘束の適応3要件が改善した場合、または身体的拘束が不要と判断した場合、医師は身体的拘束
の終了(解除)の指示を出す。看護師は指示を確認し、速やかに解除する。看護師判断で解除した場合は、事後
に医師へ報告し、指示を受けることとする。
→解除基準:身体的拘束の適応3要件が改善し、診療上の安全確保のための身体的拘束が解決できたとき、医師の指
示のもとに解除する。
①治療・処置が終了、または方法を検討して危機が回避されたとき
②患者が治療を理解し、協力が得られるようになったとき
③家族などの協力が得られるようになったとき
④回避・軽減(代替)方法が実施されたとき
4)身体的拘束を最小化するための日常ケアにおける基本方針
・身体的拘束を行う必要性を生じさせないために日常的に以下のことに取り組む。
(1)患者主体の行動や尊厳を尊重する。
(2)言葉や応対などで、患者の精神的な自由を妨げないよう努める。
(3)患者の思いをくみとり、患者の意向に沿ったサービスを提供し、多職種協働で丁寧な対応に努める。
(4)身体的拘束を誘発する原因の特定と除去に努める。
(5)基本的なケアを行い、生活リズムを整える。①起きる、②食べる、③排泄する、④清潔にする、⑤活動する、
という5つの事項について、患者個々に合った十分なケアを提供する。
5)身体的拘束以外の患者の行動を制限する行為の最小化について
・行動を制限する目的での薬剤の使用は、治療・療養上必要な場合を除き行わない。
・患者に対し、行動を制限するような言動(発言や制止など)がないよう常に意識しながら対応する。
6)鎮静を目的とした薬物の適正使用について
・当院のデルタプログラムに沿った薬剤を検討する。
・認知症患者の暴力や不穏に対する薬物療法ではリスペリドンが推奨されている。
・認知症患者の性的脱抑制、不適切な性的行動に対する薬物療法では、SSRI、非定型抗精神病薬、トラゾドンが推奨
される。
・薬物を使用した場合、その効果と副作用の評価を行い、薬物の種類、投与量、投与時間、投与方法などを調整する。
4.身体的拘束最小化、低減のための職員教育
1)全職員に、当指針を周知する。
2)定期的に、身体的拘束最小化に関する研修会を年1~2回開催する。全職員を対象とし年1回は受講できるようe-ラ
ーニング等も活用する。
3)研修の実施にあたっては、研修主催者が実施日・実施場所・参加人数・研修名・内容(研修概要)及び研修後アン
ケートを記載した記録を作成する。
5.患者・家族への不安の軽減への配慮
説明者は、身体的拘束・行動制限が人間の尊厳に関わる重大な問題であることを認識しているべきで、このことが患
者・家族に伝わることが必要である。そのためには、患者の状況について的確に説明することにより、安全確保のた
めに、やむを得ず実施することに納得が得られる必要がある。特に、看護師には、実施中の患者・家族の思いを受け
止めるような態度や言動が求められる。
解除に向けた検討の場やカンファレンスで、観察項目の確認だけでなく、患者・家族の不安を受け止めた内容の検討
が必要である。
(附 則)
この指針は、令和6年5月28日から施行する。